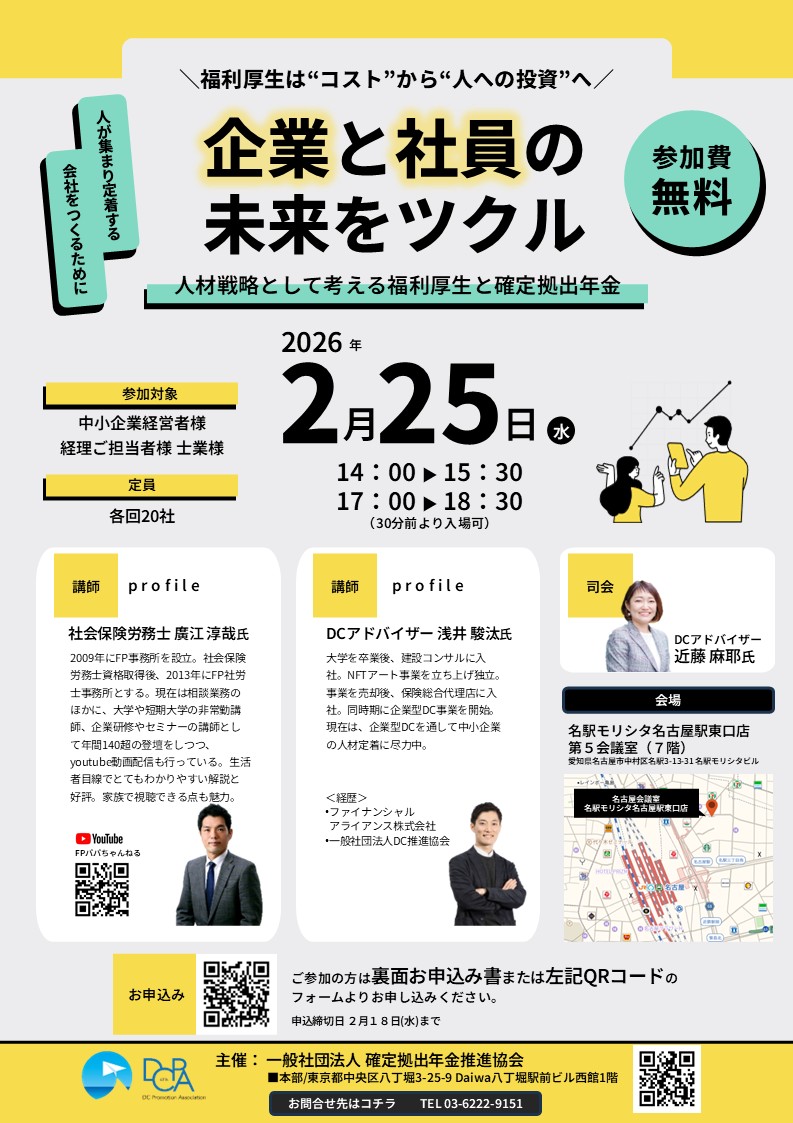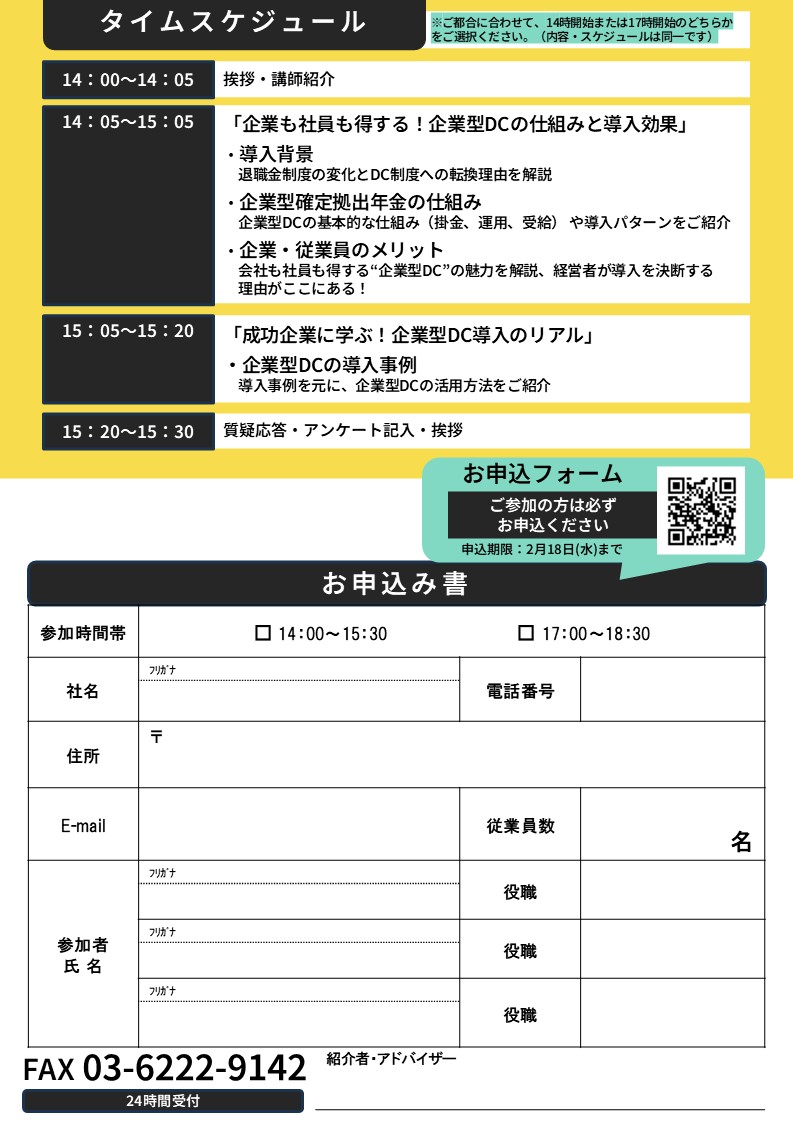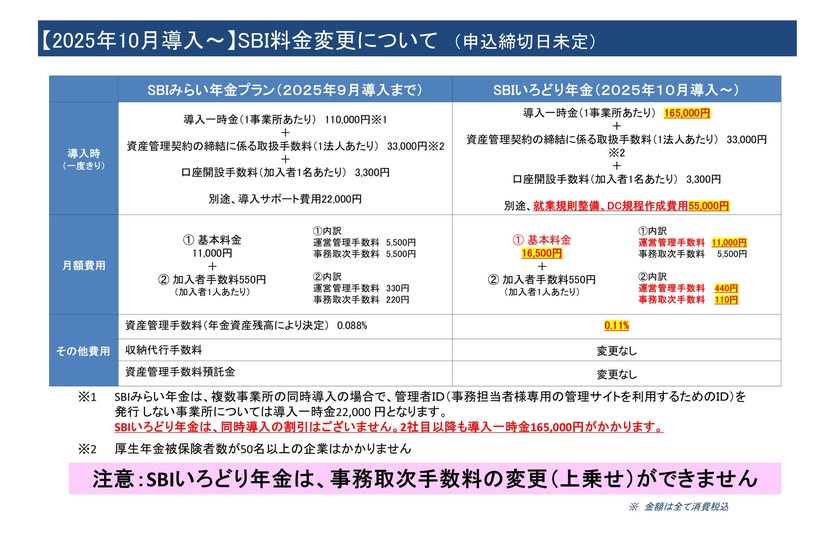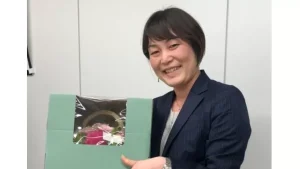確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。
内外金利差が、為替市場の需給にどう影響を与えるかを考えてみましょう。
内外金利差とは
内外金利差とは、国内の金利と外貨の金利の差です。国内の金利と外貨の金利は、それぞれ異なる要因で変動するため、内外金利差は縮小したり拡大したりします。
外貨建ての債券や預金に投資したいと考えている日本国内の投資家を想像してみましょう。
投資家は、外貨の金利が円の金利に比べて高ければ高いほど、積極的に外貨へ投資しようと考えるでしょう。そのため、内外金利差が拡大すると、外貨へ投資する魅力が高まり、外貨への需要が増えます。よって、円を売って外貨を獲得するため、円安外貨高の要因になります。
反対に、外貨の金利が低下して内外金利差が縮小すると、外貨へ投資する魅力が薄まるため、外貨への需要が減ります。よって、外貨を売って円を獲得するため、円高外貨安の要因になります。
この場合、金利とは、実質金利のことをいいます。実質金利とは、名目金利からインフレ率を差し引いた金利のことです。一般的に、新興国の金利は高いのですが、インフレ率も高いので実質金利は低かったりします。見かけの名目金利ではなく実質金利に目を向けるようにしましょう。
ところで、2022年から2024年にかけて米ドル円の相場は、115円/ドルから145円/円程度に大きく米ドル高円安に振れました。
日本と米国の金利の差を反映しています。経済成長率やインフレ率の差などから米国の方が日本よりも金利水準が高く、ドル高円安になっていったのです。
外国為替市場について
外国為替市場では円相場は日米2年金利差との連動性が高いとされています。米連邦準備理事会(FRB)の急激な利上げで米国の2年債利回りは2021年末の0.7%台から足元で4.5%程度まで上がった一方、日銀の大規模緩和の継続で日本の2年債利回りは低いままです。22年以降の円安・ドル高は日米金利差の拡大が主導してきたと言われています。
では、今後のドル円相場はどうなるのでしょうか?アメリカでは、インフレが鎮静化してきており、利下げのタイミングを計り始めました。一方、日銀は、マイナス金利の解除のタイミングを探り始めています。金利差は縮小傾向に向かいそうです。したがって、ドル安円高に徐々に向かうことが予想されます。
次回は、経常収支その他に着目して為替の変動を見ていきます。