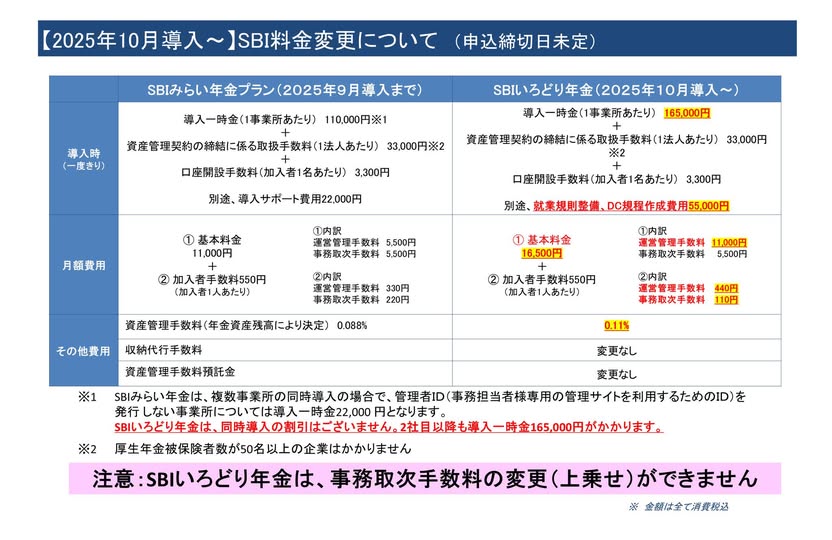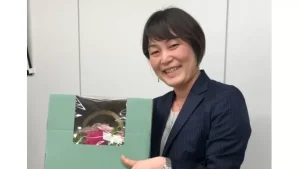確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。
最近では、中小企業にも企業型DCを導入する機運が高まってきました。企業型DCを導入する際に、まず考えなくてはいけないのが導入する企業型DCの形態です。
確定拠出年金の形態
中小企業が加入できる確定拠出年金の形態が4つあります。
①会社拠出のみ(大企業中心)
②会社拠出+マッチング拠出(大企業中心)
③完全選択制(給与減額型)
④会社拠出+選択制(一部給与減額型、A+Bとも言う)
従来、DeCoPAで取り扱っている企業型DCの形態は、圧倒的に③完全選択制(給与減額型)でした。ところが、最近になって急速に④A+Bが増えてきたのです。
A+Bは、導入する企業にとってはコストが高くなります。何故なら、企業型DCのコストは、加入人数に応じて増えていくからです。完全選択制では、加入するかしないかを従業員一人一人が選択します。加入しない人には、コストが発生せず、加入者の掛金額が大きいと社会保険の等級が下がり、会社の法定福利費が減るメリットがあります。これが、企業型DCを中小企業が導入しやすい大きな理由でもあったのです。
ところが、A+Bのおいては、選択部分を利用しない人(会社が出してくれる分のみを掛金として拠出)にも加入者としてのコストが発生します。また、選択部分を利用しない人は、社会保険料が削減される副次的効果が見込めません。
そこには、コスト高となっても社員への福利厚生を充実させようという企業の意思があると考えられます。社員の採用と定着が大きな課題であると言えるでしょう。
あるDeCoPAの確定拠出年金アドバイザーさんから聞いたのですが、経営者から「コストが高くなっても、DCを始めて運用することによって、金融リテラシー向上につながるから会社拠出+選択制にしたい。」と言われたそうです。素晴らしい経営者ですね。また、そのアドバイザーは、「毎年、投資教育をお願いします。個別面談もお願いします。」と言われたそうです。アドバイザーとして、とても嬉しいお言葉です。
会社拠出+選択制という形態
しかしながら、会社拠出+選択制という形態には、留意しなければならない項目がいくつかあります。
1, 会社拠出分に客観性はあるのか
2, 会社拠出分に事業主返還という制度を付けるのか
3, 外国人労働者への対応
4, 高齢の従業員への対応
次回より、それぞれの項目の詳細と具体的な対応を説明していきます。